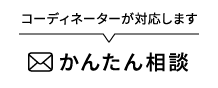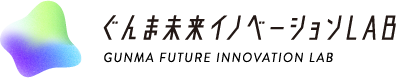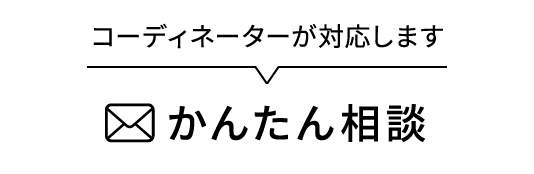PICKUP ピックアップ課題
海の善を届ける人たちへ。海老善 × 地域マッチングの未来
有限会社 海老善(えびぜん)は、群馬県佐波郡玉村町に拠点を構える海産物専門問屋です。創業以来39年にわたり、前橋・高崎・伊勢崎・桐生・太田・本庄・秩父など広範囲にわたる地域へ、鮮度と品質にこだわった海産物を届けてきました。
特に、10g単位のカットや味付け、三枚おろしなど、細やかな加工対応が強みで、飲食店や病院、保育施設などの人手不足を支える存在としても注目されています。
また、自社ブランド「スマイルシュリンプ」などのPB商品開発にも力を入れ、食の楽しさと安心を届ける企業として進化を続けています。
 イベント出店時の様子
イベント出店時の様子
また、このたび未来投資デジタル産業課のぐんま未来イノベーションLABのマッチングにより新商品「まるごと海老フライ」開発にあたり食品化学を研究する大学を推薦していただき、その後、群馬県衛生環境研究所の協力を得ることで一気に商品開発が加速しました。その商品も間もなく完成し来春(2026年)にはお披露目予定となります。
 新商品のまるごと海老フライ
新商品のまるごと海老フライ
「捨てる殻に、未来を見た」
~海老の殻から生まれた価値創造 ~
きっかけは“もったいない”という違和感
私たちは地域密着型のアットホームな会社です。日々の業務の中で、どうしても避けられないのが「海老の殻」の廃棄。鮮魚や加工品を扱う中で大量に出るこの副産物に対し長年「なんとか資源にならないか」「このまま捨ててしまうのはもったいない」という思いを抱いていました。この違和感が、やがてひとつの問いへと変わっていきます。「廃棄される殻に、何か価値は眠っていないだろうか?」と。
文献から見つけた“赤い宝石”アスタキサンチン
海老善の代表町田純やスタッフたちは、海老の殻についての文献や研究資料を調べ始めました。そこで出会ったのが、アスタキサンチンという成分。これは海老やカニなどの甲殻類に含まれる赤い色素で、強い抗酸化作用を持ち、美容や健康食品の分野でも注目されている成分です。「廃棄していた殻に、こんな栄養価があったなんて…」。驚きとともに海老善の挑戦が本格的に始まりました。
まずは“振りかけてみた”ところから
最初に試みたのは、殻を乾燥・粉砕しパウダー状にして海老に振りかけるという方法でした。しかし思うような効果は得られず、アスタキサンチンの含有量も期待したほどではありませんでした。
それでも、海老善は諦めませんでした。「どうすれば、もっと効率よく、自然な形で成分を取り込めるのか?」 試行錯誤の末、たどり着いたのが“漬け込む”という工程です。
「漬け込む」という発想が生んだ飛躍
殻をパウダーにするだけでなく、海老の身を殻の成分に漬け込むという工程を加えたことで、アスタキサンチンの含有量が増加。さらに、香ばしさや旨味も引き立ち、海老本来の魅力をより深く引き出すことに成功しました。
工程は非常に手間がかかります。大手企業であれば、効率や利益率を考えて敬遠するような領域かもしれません。しかし海老善はあえてそこに踏み込みました。
「私たちのような小さな会社だからこそ、身軽に挑戦できることがある」。その信念が商品開発の原動力となったのです。
“海老王子”というユーモアから生まれた発想
実はこのアイデアの原点には、もうひとつのユニークなエピソードがあります。代表の町田純が、数年前から「海老王子」と名乗り、海老の被り物をしてイベントやSNSで発信。様々な食のイベントに地道に参加していたのです。
「何か面白いことをして自社をもっと知ってもらえないか」。そんな遊び心から生まれたキャラクターが、やがて“殻の再活用”という真面目な挑戦へとつながっていきました。
「ふざけているようで、本気なんです」。この言葉には地域企業としての誠実さと、挑戦者としての意気込みが感じられます。
 海老王子こと海老善 代表取締社長 町田さん
海老王子こと海老善 代表取締社長 町田さん
「縁と知恵が育てた、海老フライの物語~前編~」― データと出会い、そして“海なし県”からの挑戦 ―
データが支えた、確かな裏付け
想いだけでは商品は生まれません。「本当にアスタキサンチンが増えているのか?」「どの工程が最も効果的なのか?」。その問いに答えるためには、科学的な裏付けが必要でした。
そこで出会ったのが、群馬県が運営する「ぐんま未来イノベーションLAB」。このマッチング支援を通じて、大学機関との連携が実現。さらにそのご縁から、群馬県環境衛生研究所を紹介していただき、検体実験を繰り返すことができました。
連携によって漬け込み工程を加えた海老フライから、通常の1.8倍のアスタキサンチン含有量が検出されるという確かなデータが得られたのです。「これなら、自信を持って世に出せる」 科学的な裏付けが開発チームの背中を押しました。
“縁”がつないだ知恵と挑戦
挑戦の裏には、常に“人との縁”がありました。ぐんま未来イノベーションLABとの出会い、大学機関との連携、研究所の協力。どれも偶然ではなく、日々の誠実な仕事と地域とのつながりが育んできた信頼の結果です。
「新しいことに挑戦するのは、いつだってリスクがあるが、出会った人たちの知恵と応援があるから、私たちは前に進める」。“海老王子”としてのユニークな発信の裏には地域とともに歩む企業としての覚悟がにじんでいます。
加工所が手狭に。次なる一歩へ
挑戦を重ねる中で海老善の加工所は次第に手狭になっていきました。新たな商品開発、受注の増加、そして直販へのニーズの高まり新たな加工所の建設が決定しました。
そして、社員全員の声から生まれたもうひとつのプロジェクトが、直売所のオープンです。 「BtoBだけでなく、お客様の喜ぶ顔も見たい」。この思いが加工所の隣に直売スペースを設けるという構想につながりました。
“海なし県”から届ける、海の恵み
群馬県は“海なし県”として知られています。 しかし、海老善はその地の利を逆手に取り、「だからこそ、鮮度と品質にこだわる」という姿勢を貫いてきました。
問屋としての目利きと流通の強みを活かし、高付加価値の海産物を地域のお客様に直接届ける。単なる販売ではなく、「海の恵みを届ける」という使命感に近いものです。
「海がないからこそ、海を大切にできる」 そんな逆説的な誇りが海老善の根底には流れています。
「パン粉の出会いが、海老フライを完成させた~後編~」― 有限会社海老善が挑む、味と想いのかたち ―
“縁で商売する”という哲学
地域密着型の会社ですから、根底にあるのは、「縁で商売する」という哲学。人との出会い、地域とのつながり、素材との巡り合わせを大切にしながら日々の仕事に向き合っています。
海老善が、いま力を注いでいる「まるごと海老フライ」は、単なる加工食品ではなく“想いを包んだ一品”として細部にまでこだわり抜いた商品です。
パン粉との出会いが、味を決定づけた
海老フライの開発において、実は最も時間をかけたのが「パン粉選び」でした。「衣は脇役ではなく主役の海老を引き立てる舞台装置のようなもの」。そう考え何度も試作を重ね、ようやくたどり着いたのが、あるパン屋さんとの出会いでした。
食品添加物不使用で国産小麦の天然酵母パンを粉にして使うことで、海老との相性が格段に向上。パン粉は焙焼式のため、香ばしさと深みが加わり、海老フライの味わいが一気に完成に近づいたのです。 「このパンとの出会いがなければ、今の味にはたどり着けなかった」。こう語る開発チームの言葉には素材への敬意と感謝が込められています
“スマイルシュリンプ”に込めた想い
ここで海老善の自社ブランド「スマイルシュリンプ」についても触れておきます。 これは、無保水・無添加にこだわった海老で、ぷりっとした食感と自然な旨味が特徴です。無保水海老とは保水剤(リン酸塩などの食品添加物)を一切使用していない、海老本来の味と食感を大切にした海老です。
「余計なものを加えず、素材そのものの力を信じたい」。こうして生まれたスマイルシュリンプは、まさに“笑顔を届ける海老”として、健康志向の方や小さなお子様にも安心して召し上がっていただけます。無保水海老は、手間と管理を惜しまない加工によって、海老本来の美味しさを最大限に引き出した逸品です。 海老善の「スマイルシュリンプ」はまさにその代表格と自負しています。 “プリプリ”だけではなく、“ギュッと旨い”。無保水海老の真価です。
魚の加工から始まった“あと一手間”のサービス
実は、海老善の「美味しいものを届けたい」という想いは7年前の魚の加工から始まりました。問屋として卸していたお得意先にもっと喜んでもらいたいと、切り身や味付けなどの加工をスタート。特に、介護施設や幼稚園など、調理の手間を減らしたい現場にとって“あと一手間”で完成する魚料理は大きな助けになっています。
「魚の卸だからこそできるサービスを」。その姿勢が、やがて海老フライやPB商品の開発へとつながっていきました。
「縁を育てる海老フライ」プロジェクトからの呼びかけ
~ 一緒に“こんなことやってみたい”を形にしませんか? ~
私たち海老善は、これまでも、そしてこれからも “縁で商売をする”という姿勢を大切にしていきたいと考えています。
今回の海老フライ開発はまさにその象徴でした。素材との出会い、研究機関との連携、パン屋さんとの協働、地域のお客様とのつながり。すべてが「縁」から始まり、「知恵」と「挑戦」で育まれてきました。
そして今、私たちはこのプロジェクトを通じて、新たな縁を育む仲間を探しています。「こんなこと、やってみたい」。熱い想いを持つ方と出会い一緒に次の一歩を踏み出したいのです。
ピックアップ課題と、マッチングの可能性
海老フライをもっと多くの人に届けたい
課題として販路の拡大と、商品の魅力を伝える発信力がまだ足りていません。SNS運用や動画制作が得意な方と協働し商品の魅力を伝えるSNS発信をサポートしてくれる方を探しています。
直売所を“体験の場”にしたい
ただ売るだけでなく、地域の人が集い、学び、楽しめる場にしたい。食育イベントやワークショップを企画できる教育関係者や料理研究家の皆様とのコラボも楽しみにしています。
さらに、地域の高校・大学と連携し、学生との共同プロジェクト(商品開発・販売体験など)による次なる一手に参加してもらいたいです。
“捨てない加工”をもっと広げたい
また、「海老の殻を活かした商品開発は進んでいますが、他の副産物にも可能性があるのでは」と可能性を探っています。ですから、サステナブルな活動に御興味を持たれている食品ロスやアップサイクルに関心のある研究者・スタートアップ皆様とのコラボをさせていただきたいです。加えて、化粧品・健康食品分野での応用を模索する企業や開発者の皆様にも「海産物の廃棄」の有効利用に興味を持っていただけましたら嬉しいです。
地域とともに“お披露目”の場をつくりたい
2026年春に誕生する海老フライを地域の皆さまに直接味わっていただける機会をつくりたいです。地域貢献や地産地消をテーマにしたイベントなど、海老フライを提供・紹介していただける場を探しています。
「2026年春、私たちの海老フライが地域の笑顔とともにお披露目されること」。それが、私たちにとって何よりの喜びです。地域の食卓に、新しい物語を届ける場を一緒につくっていただけたら嬉しいです。
~おしまいに~
一緒に育てる、これからの“縁”
私たちは、完璧な答えを持っているわけではありません。でも、「やってみたい」という気持ちと、「誰かと一緒に育てたい」という想いがあります。
もし少しでも 「これ、関われるかも」「一緒に面白いことができそう」。そんな気持ちが芽生えたなら、ぜひ声をかけてください。
海老フライをきっかけに “縁”が“挑戦”に変わり、“未来”へとつながっていく。そんな物語を、これから一緒に紡いでいきませんか?
 左:海老善 代表取締役社長 町田さん 右:インタビュアー 奈良さん
左:海老善 代表取締役社長 町田さん 右:インタビュアー 奈良さん
【テキスト&インタビュー】
アナウンサー 奈良のりえさん
【プロジェクトに対する問い合わせ対応】
ぐんま未来イノベーションLAB お問い合わせフォーム よりご連絡ください。